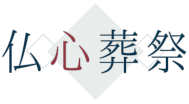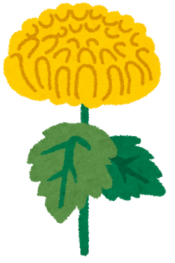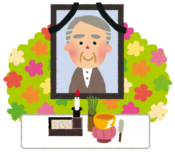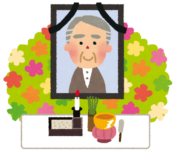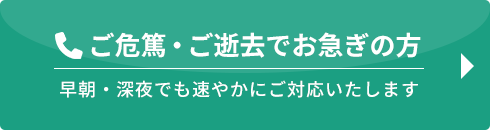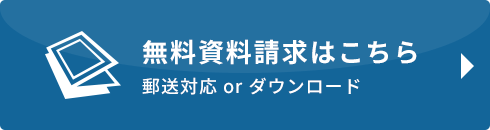葬儀の資金や費用を準備するポイント

葬儀の資金や費用に関しては、今も昔も変わらず問題になることがあります。
葬儀は突然のことで精神的にも負担が増えていますし、葬儀までの時間にも制限があります。そのためじっくり時間をかけて調べることが難しいもの。
葬儀で失敗したなという経験がある方なら、「あのとき、もう少し落ち着いて調べておけば」という後悔があるかもしれません。
そこで今回は、あなたのように検索することで必要な情報を知り、落ち着いて葬儀を行うために大切な資金と費用についてお話していきます。
1: 葬儀の資金はいくら必要?
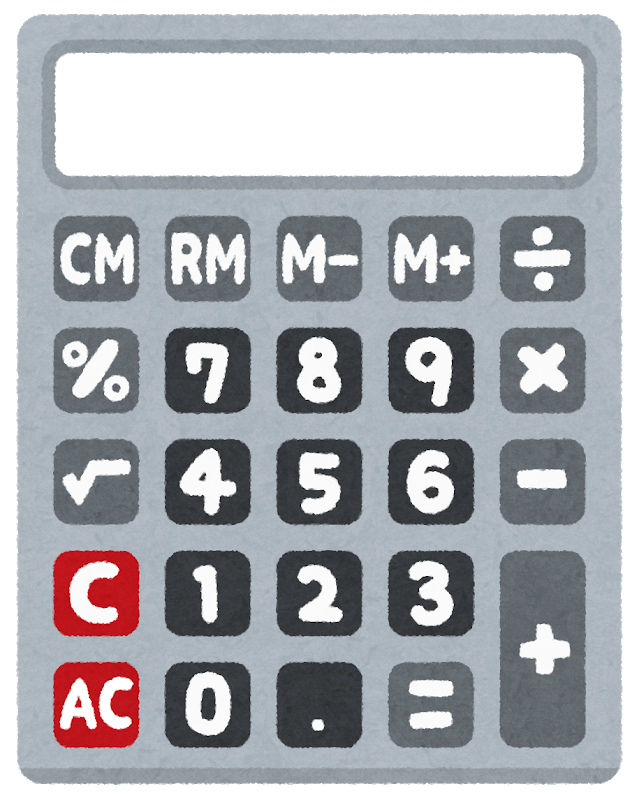
葬儀の資金というと、いくらくらい必要だと予想されているでしょうか。
日本消費者協会が2017年に調査した葬儀に関するアンケート結果によりますと、葬儀費用の平均総額は196万円ということなのです。
この平均総額には、
- 葬儀一式の費用
- 通夜や告別式の飲食や接待費用
- お布施
こういった内容が含まれています。
ただし、通夜や告別式への参列者の人数によっては、飲食費や返礼品にかかる費用が増えることになりますので、おおよその目安として200万円くらいは必要になるということです。
この費用は必要なことですし、故人とのお別れのときですから金額だけで良い悪いを判断することはできません。ただ、「200万円という費用が突然必要になる」、この突然さが多くの方の負担になっていることは間違いないでしょう。
2: 葬儀の資金に含まれる費用とは

200万円という葬儀の費用には、どのような内容が含まれているのでしょうか。少し内訳を知っておきましょう。
(1)儀式の費用
葬儀のお見積もりでは「葬儀一式」と書かれている部分です。
- セレモニーホールを使用する費用
- 祭壇の費用
- 棺の費用
- 遺影の費用
こういった内容が基本です。そして、
- セレモニー当日の司会者の費用
- スタッフの費用
- 寝台車や霊柩車の費用
- 火葬料
も必要なので、一緒にプラスされていることがほとんどです。
(2)接待の費用
お通夜や葬儀では接待が必要になることもあります。これは地域やご親族同士の考え方で変わってきます。
- 親族や関係の近い方へお出しする飲食費
- 弔問いただいた方へお渡しする返礼品の費用
飲食費に関しては、食べ物はある程度コースが決まっていますので、大きな増加は出ないことが多いですが、飲み物に関しては増加する可能性があります。ついつい飲み過ぎてしまわれる方もいらっしゃいますので、難しい部分ですね。
また、返礼品は弔問される方の人数によって変化しますので、想定よりも多くの方が弔問された場合は費用も増えることになります。
(3)お布施という費用
難しいと言われるのがお布施です。
いったいいくらくらいが適切なのか判断が難しいところです。
ただ、最近は菩提寺の方へ前もってお伺いしておくのは失礼ではありませんので、悩んだときはお聞きになることをおすすめしています。
3: 葬儀費用で注意するポイント

葬儀費用で注意するポイントは2つあります。
(1)追加費用
葬儀の費用には、葬儀社によって様々なプランが用意されています。
これらのプランは葬儀までの時間が少ない中で、不足無く選べるため便利な内容なのですが、きちんとプランの内容を確認しておかないと追加費用が発生することもあります。
例えば、故人の体を洗って清めるサービスがプランに入っているところとそうでないところがあります。
もし以前出席した葬儀でやっていたから、自分たちのときも「やって当然」だと思い、プラン内容を確認せずに「湯かんもお願いできますか」と言ったとすると、請求書を見たときに追加費用になっていたということもあります。
また、実際に葬具を見たときに、故人を想い、もう少し違う骨壺にしてもらおうと考えお願いすると、葬儀社はご対応させていただきますが、プラン内ではなくグレードアップへの変更となり追加費用として請求書へ盛り込まれていることもあります。
追加費用になるかどうかは見積もり段階でしっかり確認するとわかりますが、実際のところはそういう気持ちになれないのが現実です。
「葬儀でお金のことを聞くなんて」と考えられるかもしれませんが、プラン決定後に葬儀社へ何かをお願いするときは、追加費用が必要なのかどうかを確認しておきましょう。
もうひとつ追加費用として注意しておくことは、先ほども出てきましたが「飲食費用」「返礼品」によって変わるということです。こればかりは「人数を超えたので帰ってください」とは言えませんし、親族の中で「飲み過ぎる」方がいたとしても「飲まないでください」とは言えません(言うとややこしいトラブルになる可能性が高いです)ので、費用に少し余裕を見ておくのが精神衛生上も良いかと思います。
(2)後日必要になる費用
家族葬や直葬など、身近な方だけで静かに葬儀を行った場合、葬儀が終わってからお聞きになった方がご家庭へ「弔問」へ来られることもあります。
こういう場合、お茶菓子やお返しが必要になり費用が発生するケースも出てきます。
また、お金という費用だけではなく、
- 頻繁に弔問いただくと家族がゆっくり休めない
- 好きに出かけることができない
- なかなか帰っていただけない
時間という費用が必要になるケースも多々あります。
わざわざご自宅まで弔問いただくことは大変ありがたいことですが、負担になることもあります。
4: 葬儀の資金や費用を準備しづらいときは

200万円という金額や、追加費用が必要になるかもしれないと聞くと、葬儀費用をどうやって準備すれば良いのか悩んでしまうかもしれません。
また、いくら悩んでも解決策が出てこず、準備したくてもしづらいこともあるでしょう。
そういった場合は次からお伝えする方法を検討してみてはいかがでしょうか?
(1)葬儀を小さく簡単にする
家族葬や直葬などを検討してみるのはいかがでしょうか。
家族や関係の近い人だけで静かにお別れができますので、費用も少なく気兼ねも少なく葬儀を行うことができるでしょう。
仏心葬祭の場合ですと家族葬なら30万円から行うことができます。また、読経に関しては私自身がお寺で修行し学ばせていただいているため、宗教者でなくてもよろしければ私がお布施をいただくことなく読経をあげさせていただくことも可能です。
(2)市民葬
自治体によって細かな内容が異なりますが、一般的な葬儀よりも少ない費用で済ますことができます。
お亡くなりになった方の住民票がある自治体の窓口へ相談してみてください。
(3)クレジットカード
クレジットカードで葬儀費用をお支払いいただけるところも増えてきています。
葬儀社を選ぶときに「クレジットカードが使えますか」と聞いておきましょう。同時にグレジットカードの限度額は注意が必要です。いざクレジットカードで決済しようとしたとき、限度額オーバーになると葬儀の形式を変更するか現金で支払うことになります。
5: まとめ
葬儀の費用はけっして安くはありません。そのため生前から葬儀社と相談し資金を準備しておくのが理想的です。
そして、いざ葬儀のときは、冷静に内容と費用のバランスを考えるようにしてください。